雑誌「自遊人」が運営。無添加・オーガニック・魚沼産コシヒカリ 「オーガニック・エクスプレス」
- カテゴリ
- 商品検索
- カート
- 当日発送・定期便
- 平日14時迄は即日発送
- 便利な定期配送便
- おトクな会員サービス
- 送料無料
- produced by 自遊人
里山十帖 - おすすめ別
- メディアで紹介された品
- new! & 再入荷
- キャンペーン
- 感謝のきもち、ギフト
- オリジナル食材
- お米
- 無添加ごはんのおとも
- 天然&無添加
木桶味噌・調味料 - 伝統製法の出汁
- 豆・雑穀
- オーガニック&無農薬
西日本の野菜セット - オーガニック&無農薬
野菜ジュース - ハーブティー
コーヒーほか - 米菓・おやつ
- 非常食・保存食
- 台所道具
- 産地からお届け
- こだわり麺
- 海の幸&山の幸
- フルーツ
- スイーツ&お菓子
- おもてなしに活躍!
- 天然素材の雑貨・家具
- 寝具・布団
- 衣類
- 生活雑貨
- 家具
- 雑誌「自遊人」
- 定期購読
- バックナンバー
読み物一覧
職人がいるからこそ守られてきた、200年前からの伝統製法。和三盆糖
自遊人編集部
〜 『自遊人』特集「伝えたい味。」より転載〜
2018.03.13

Index
奈良時代には、調味料ではなく薬として扱われていました。
日本独自の伝統的な砂糖、和三盆糖。
200年前からの伝統製法を守れるのは職人がいるからこそ。
奈良時代には、調味料ではなく薬として扱われていました。
奈良時代に鑑真が持ち込んだとされる砂糖。
当初は調味料ではなく薬として扱われたため、大仏に奉納されたという記録が残っています。
当然、庶民の口に入るものではなく、室町時代から戦国時代にかけて輸入量が増したものの、まだまだ高嶺の花的存在でした。
調味料として庶民が使えるようになったのは江戸時代。肉体労働者が多かった江戸の料理には甘辛いものが多く、砂糖は彼らの労働の疲れを癒していたと思われます。
原料はサトウキビもしくは甜菜。製法によって大きく二種に分かれ、ひとつが原料からとった液体をそのまま濃縮結晶化させた「含蜜糖(がんみつとう)」で黒砂糖が代表的存在です。
もうひとつがそこから糖蜜を分離させて造る「分蜜糖(ぶんみつとう)」で、製法によりさらにいくつかに分類されます。
日本で最も多く販売されているのが 「くるま糖」。精製度合いによって上白糖、中白糖、三温糖に分かれています。上白糖はいわゆる白砂糖で、ブドウ糖と果糖を合わせた転化糖を加えています。国産サトウキビを原料にするほか、海外から粗糖といわれる原料糖を輸入し、精製・加工したものも多く出回っています。
当初は調味料ではなく薬として扱われたため、大仏に奉納されたという記録が残っています。
当然、庶民の口に入るものではなく、室町時代から戦国時代にかけて輸入量が増したものの、まだまだ高嶺の花的存在でした。
調味料として庶民が使えるようになったのは江戸時代。肉体労働者が多かった江戸の料理には甘辛いものが多く、砂糖は彼らの労働の疲れを癒していたと思われます。
原料はサトウキビもしくは甜菜。製法によって大きく二種に分かれ、ひとつが原料からとった液体をそのまま濃縮結晶化させた「含蜜糖(がんみつとう)」で黒砂糖が代表的存在です。
もうひとつがそこから糖蜜を分離させて造る「分蜜糖(ぶんみつとう)」で、製法によりさらにいくつかに分類されます。
日本で最も多く販売されているのが 「くるま糖」。精製度合いによって上白糖、中白糖、三温糖に分かれています。上白糖はいわゆる白砂糖で、ブドウ糖と果糖を合わせた転化糖を加えています。国産サトウキビを原料にするほか、海外から粗糖といわれる原料糖を輸入し、精製・加工したものも多く出回っています。

日本独自の伝統的な砂糖、和三盆糖。
一方、日本独自の伝統的な砂糖が和三盆糖。
原料は沖縄などで栽培されるサトウキビよりも細い、竹糖と呼ばれる在来種サトウキビ。八代将軍吉宗は全国にその栽培を奨励し、積極的に栽培した高松藩、徳島藩で生まれた和三盆は両藩の名物に。現在も香川産は讃岐和三盆、徳島産は阿波和三盆と呼ばれ脈々と受け継がれています。
竹糖を砕いて圧搾し、煮詰めて結晶化させた白下糖から糖蜜を抜く「研ぎ」という作業が、 和三盆独自の技術。徳島県には5軒ほど製糖所がありますが、 この伝統製法を守り続け、ほとんどの工程を手作業で行っているのが岡田製糖所です。
「もともと農閑期の仕事として始まった地域の産業。私が子どもの頃と同じ作り方、昔通りの作り方を続けてきただけなんです」と笑う社長の岡田和廣さん。
押し槽と呼ばれる、てこの原理を利用した箱の中に白下糖を入れて圧力をかけ、含まれる糖蜜をゆっくり押し出していくと白下糖は色が抜けて白くなっていきます。さらに水を加えて練ることで糖蜜を溶け出させ、また押し槽に入れて圧力をかけて、という作業を繰り返すことで徐々に白くしていきます。
原料は沖縄などで栽培されるサトウキビよりも細い、竹糖と呼ばれる在来種サトウキビ。八代将軍吉宗は全国にその栽培を奨励し、積極的に栽培した高松藩、徳島藩で生まれた和三盆は両藩の名物に。現在も香川産は讃岐和三盆、徳島産は阿波和三盆と呼ばれ脈々と受け継がれています。
竹糖を砕いて圧搾し、煮詰めて結晶化させた白下糖から糖蜜を抜く「研ぎ」という作業が、 和三盆独自の技術。徳島県には5軒ほど製糖所がありますが、 この伝統製法を守り続け、ほとんどの工程を手作業で行っているのが岡田製糖所です。
「もともと農閑期の仕事として始まった地域の産業。私が子どもの頃と同じ作り方、昔通りの作り方を続けてきただけなんです」と笑う社長の岡田和廣さん。
押し槽と呼ばれる、てこの原理を利用した箱の中に白下糖を入れて圧力をかけ、含まれる糖蜜をゆっくり押し出していくと白下糖は色が抜けて白くなっていきます。さらに水を加えて練ることで糖蜜を溶け出させ、また押し槽に入れて圧力をかけて、という作業を繰り返すことで徐々に白くしていきます。

200年前からの伝統製法を守れるのは職人がいるからこそ。
「研ぎの作業を3回繰り返したから三盆糖という名前がついたんです。今では4、5回行います。加える水の量、回数などすべて職人の勘が頼り。
彼らがいるから、機械化しないでやってこれたんです。最近では和菓子だけでなく、洋菓子や料理にも幅広く使われるように。支持してくれる人がいる限り、この伝統を守っていきたいですね」
(雑誌「自遊人」2015年5月号に掲載)
彼らがいるから、機械化しないでやってこれたんです。最近では和菓子だけでなく、洋菓子や料理にも幅広く使われるように。支持してくれる人がいる限り、この伝統を守っていきたいですね」
(雑誌「自遊人」2015年5月号に掲載)

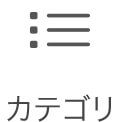














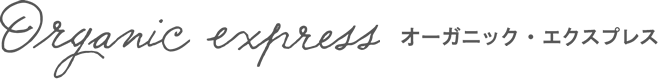
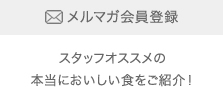

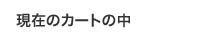
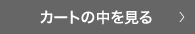










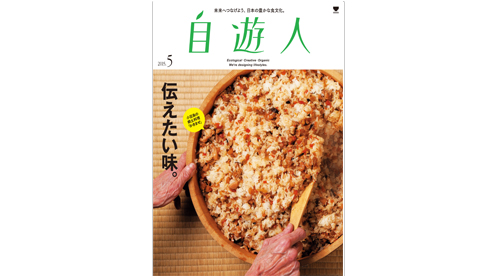









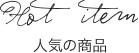













![天然由来成分100%「ノンシリコンシャンプー・トリートメント〈余[yo]〉」](/upload/save_image/03062252_5e62558784746.jpg)


日本独自の伝統製法で造られた和三盆糖は、
今や流通量ごくわずかの希少品です。